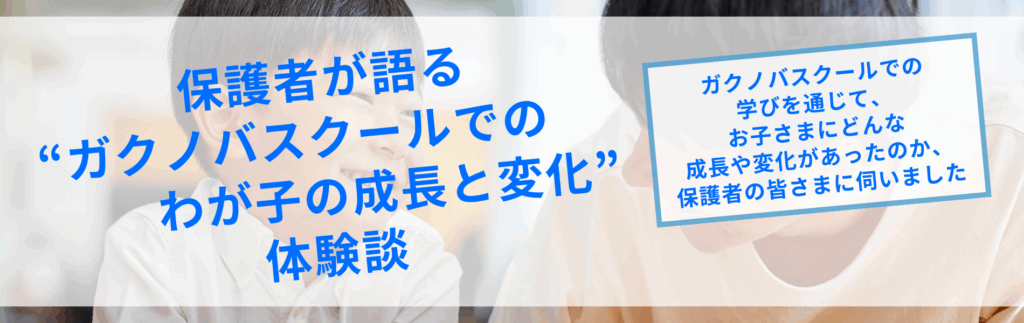

小学校5年生 保護者の声
「学校と違うところは?」と
聞いてみたら
不登校になり部分登校を10カ月ほどして、完全不登校となり2〜3週間経った頃でした。私もどうしたらいいのか悩んでいました。祖父が新聞記事の切り抜きを持ってきたのがきっかけで、オンライン説明会を受けました。その最後に先生が息子に呼びかけてくれたり、話をしているうちに興味を惹く話題があり、「見に行ってみようかな」と体験の約束ができました。
体験の日は、嫌がらずに行き、ガクノバスクールの他の子とも遊んでいました。また、行きたいか聞くと、「行きたい」と言うので申込みました。 次の登校日は、渋りながら行ったものの先生の顔を見てすぐ帰宅。いいよ、と先生が言ってくださったので、気楽に感じたかも知れません。 毎日昼間はゴロゴロダラダラ過ごしていましたが、行けた日は、昔に作った工作やおもちゃを出してきて、私に話しかけてきたのを覚えています。 だんだん慣れてきたのが、1ヶ月くらい経ってからでした。「行かなければならない」と積極的に行くようになりました。
息子は、友達と遊ぶのが好きな小学生です。不登校になって意欲がなくなり、友達と遊んだりいろいろな体験をする機会もなくなってしまい残念に思っていました。 加えて、成長するにつれ、小学校での負担も増え、生活面でもできて当たり前なことを厳しく言いすぎていたかも、と思いました。本人のペースを無視しすぎていたかも知れません。 子供が不登校になり、改めて考えさせられました。
息子に「学校と違うところは?」と聞くと、「急かされないところ」と言いました。少人数なところが、わが子には合っているのかも知れません。小学校では自分の意見を伝えたりするのができてない様子でしたが、ガクノバスクールでは自分のことを先生に話したりしているようで、一人一人の子どもの声を聞いてくれているのが、本人にとって嬉しいことだなと思っています。

中学校1年生 保護者の声
「学校に行かせたい」から
「息子らしく過ごしてほしい」へ
息子は小学1年の頃より登校しぶりや不登校でした。原因といってもはっきりしたものはなく、環境の変化に慣れにくい、過度にまわりを気にしてしまうなどの様子もあり、学校の集団生活には苦手な部分が多くありました。小学校へは最後は慣れていき、通うことができていた中、中学入学という新たな環境変化になかなか馴染めず、ふたたび自宅にこもるようになりました。
親としては、自宅でいても身体も動かせない、昼夜逆転になりがち、ゲームばかりをしがちな生活をなんとかしたいと思うものの、学校にいかせることを目標とすると本人にとっては精神的負担になってしまい心身ともに疲弊していきました。そんな中、オルタナティブスクールというスタイルをインターネットで検索しはじめたところ、ガクノバスクールを見つけました。
勉強や集団生活のようなきまりにとらわれないフリーな形、本人の自己肯定感を高めていくという考えに、ここなら息子らしくすごせることができるのではと見学に行き、入学しました。
入学してからは、学年は違えど自然と友達ができ、公園で元気に身体を動かしたり、料理づくりやスライム作り、科学センターに見学にいったりと自分たちがやりたいことに取り組み達成するという学びを得るようになりました。そして、ガクノバ楽しい、また行きたいと毎回楽しみになり元気な姿がみられるように。
気持ちが明るくなったことや、外にでる機会が増えたことで、学校へも少しずつ足をはこべるようになり、現在ではガクノバ、学校と予定をわけて前向きにすごせるようになりました。
また、登校日には、先生が明るく笑顔でいつもむかえてくれるので安心して通うこともできています。また、親としても漠然とした悩みや不安が安心に変わり、希望がもてるようになり大変感謝しています。
これからも、楽しく息子らしくガクノバスクールとともに成長していけたら嬉しいです。
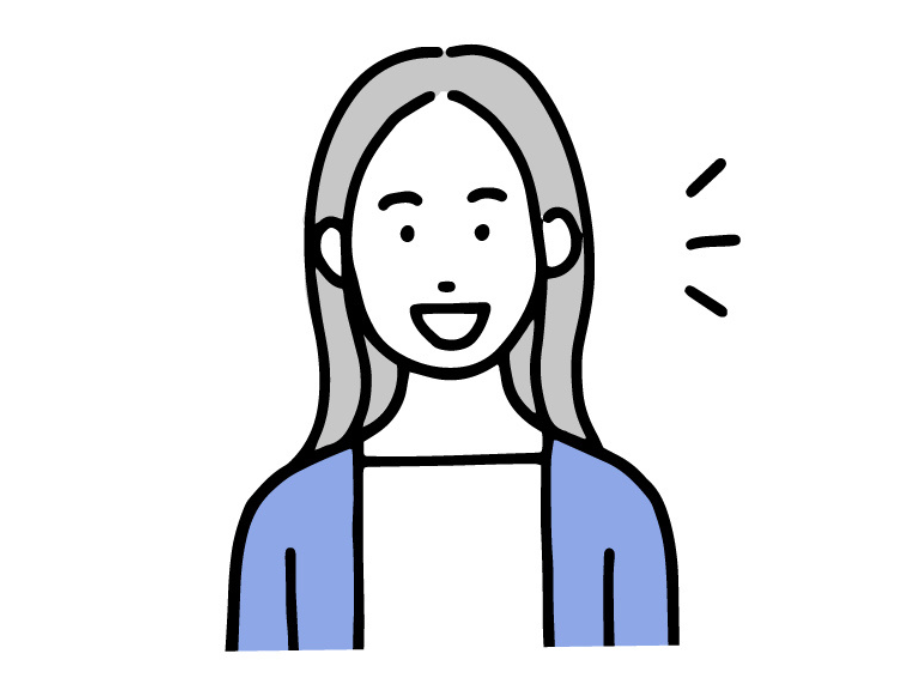
小学校4年生 保護者の声
「行きたい」と「やってみたい」が
増えていく毎日
小学校では、息子にとって苦手な事が多々あり、本人自身も劣等感や無力感、不安を強く感じている様子でした。友達は出来ましたが、学校生活にはなかなか馴染めず、不登校気味になっていき、一時期は大好きなアウトドアやお出かけにも行きたがらない様子が見られました。 少しずつそんな状況にも慣れていきましたが、相変わらず学校には時々行く程度で、それ以外は家でゲームをしたり、あまりぱっとしない日々でした。
元々探究心は旺盛で、やりたい事には積極的なタイプだったので、自由な時間を過ごせるガクノバスクールなら、きっと息子に合うだろうと思い入学しました。本人も、「自由」「少人数」「厳しくない」というキーワードに惹かれ、体験の時からとても楽しそうで積極的に参加する様子が見られました。 毎週火曜日と金曜日が楽しみになり、表情もイキイキしてきて、日常生活においてもやりたい事や新しい事に積極的にチャレンジするようになったような気がします。 少しずつですが、小学校に登校する頻度も増えてきています。
